「総移動距離は同じだが、片方の群は頻繁に立ち止まっているように見える…」
「薬剤を投与したら、動物が同じ場所をクルクルと回り始めたが、これをどう定量化すればいいのか?」
このような、行動の量的な変化から一歩進んだ「質的評価」へのニーズに応えるのが、Be-Chaseの「停止」と「回転」の分析機能です。これらの指標は、動物の不安、恐怖、記憶、あるいは運動機能の異常といった、目には見えない内的状態を解き明かすための鍵となります。
この記事では、すくみ行動(フリーズ)や回転行動(サーキリング)をどう検出し、どのような研究に活用できるのかを、具体的な研究事例を交えて分かりやすく解説します。
「停止 (Stop)」分析:不安・恐怖・休息の指標
ターゲットがほとんど動かずに一定時間留まる行動を「停止」として検出し、その回数や時間を分析します。Be-Chaseでは、ターゲットの重心がごく狭い範囲(体長の半分の半径の円内)に2秒以上留まった場合に「停止」と判定します。
得られる主要データ
- 総停止回数: 全計測期間における停止の総回数。
- 総停止時間: 全ての停止イベントの継続時間を合計した時間。
- 平均停止時間: 1回あたりの停止時間の平均。
- 各停止の継続時間: 個々の停止イベントがそれぞれ何秒続いたかのリスト。
どのような研究に役立つか?
この「停止」という指標は、以下のような様々な内的状態を反映していると考えられます。
- 不安様行動・恐怖記憶の評価:
- すくみ行動 (Freezing)の指標として利用できます。例えば、恐怖条件付け試験において、特定の音を聞かせた際の停止時間の増加は、恐怖記憶の強さを客観的に示します。
- 探索行動と休息の区別:
- 長時間の停止は、休息や睡眠状態を示している可能性があります。概日リズム分析で、活動期と休息期を明確に区別するのに役立ちます。
- 薬効評価:
- 抗不安薬や鎮静作用のある薬剤が、停止回数や時間をどのように変化させるかを評価します。
【研究での活用事例】停止分析が明らかにした恐怖記憶の脳内メカニズム
「停止(フリーズ)」反応は、条件付け恐怖実験における典型的な行動指標の一つです。権威ある科学誌Natureに発表された研究では、この停止行動を中心指標として用い、恐怖記憶の表出を制御する前頭前皮質の回路メカニズムを解明しました。
- 研究の目的: 恐怖条件付けによって獲得された記憶が、どの脳内ネットワークで制御され、どのように行動として表出されるかを理解すること。
- 停止分析の活用: マウスに音刺激(CS)と電気ショックを結びつける恐怖条件付けを行い、CS 単独提示時にマウスがフリーズ(停止)している総時間を定量化。これを恐怖応答の指標として、神経操作群と対照群で比較しました。
- 明らかになったこと: 前頭前皮質 (特に dorsomedial PFC) におけるパルブアルブミン陽性抑制性ニューロン (PV interneurons) を光遺伝学的に操作すると、停止時間(フリーズ応答)の発現が変動。PVIN 活性を抑制すると、投射ニューロンの同期性が変化し、恐怖行動が促進されるなど、特定細胞群の因果的役割が示されました。
このように、定量化された停止時間(行動レベル指標)を、神経操作との対応関係に照らして読み解くことで、見えない「記憶」や「情動」が働く神経回路への理解を深める強力な手がかりとなりました。
※本研究はBe-Chaseが使用されたものではありません。一般的な停止時間の分析を活用した研究事例としてご紹介しています。
引用元論文: Courtin, J., Chaudun, F., Rozeske, R.R. et al. Prefrontal parvalbumin interneurons shape neuronal activity to drive fear expression. Nature 505, 92–96 (2014).https://www.nature.com/articles/nature12740
「回転 (Rotation)」分析:運動機能や常同行動の指標
ターゲットが同じ場所で旋回するような円運動を「回転」として検出し、その方向や回数を分析します。
回転分析で得られるデータ
Be-Chaseでは、軌跡の角度変化が累積して360度を超えた場合に1回の「回転」として検出します。これにより、以下の指標データが得られます。
- 回転方向: 時計回り(CW)か、反時計回り(CCW)か。
- 回転回数: 方向別の総回転回数。
- 各回転の詳細: 1回の回転にかかった時間、半径、軌跡の真円度など。
- 回転軌跡の可視化画像: 検出された回転運動の軌跡を、方向別に色分けして描画した画像。
回転分析の活用法
この特徴的な行動は、特定の神経科学・薬理学研究において重要な意味を持ちます。
- 神経科学・薬理学研究:
- パーキンソン病モデル動物や、ドーパミン作動薬を投与した動物では、一方向への回転行動(Circling)が顕著に現れることがあります。この分析は、そうした運動系の異常を定量的に評価するのに不可欠です。
- 脳の片側に障害を持つモデルでは、障害側とは反対方向への回転が見られることがあり、その重症度評価や治療効果の判定に利用されます。
- 常同行動の評価:
- 特定の状況下で繰り返し行われる回転行動は、ストレスや不安レベルを示す常同行動の一種として解釈されることがあります。
- 特定の状況下で繰り返し行われる回転行動は、ストレスや不安レベルを示す常同行動の一種として解釈されることがあります。
【複合解析の真価】空間分析と組み合わせて行動を立体的に捉える
ここまでにご紹介してきたこれらの質的分析の真価は、他の記事で解説している空間分析(チェックエリア)と組み合わせた時に発揮されます。
- オープンフィールド試験での応用:
- チェックエリアで設定した「中央」と「壁際」エリア、それぞれの総停止時間を比較します。中央エリアでの長い停止は「探索前の情報収集」や「大胆さ」を、壁際エリアでの長い停止は「不安によるフリーズ」を示唆するなど、場所と組み合わせることで停止の解釈が深まります。
- 新規物体認識試験での応用:
- 新規オブジェクトを囲うチェックエリアに進入してから退出するまでの滞在中の停止回数や時間を分析します。頻繁に短く停止する場合は「対象への詳細な調査・嗅ぎ行動」を、長く停止する場合は「警戒」を反映している可能性があり、認知行動の質を評価できます。
- Y字迷路・T字迷路での応用:
- アームの分岐点(選択点)をチェックエリアとして設定し、そこでの回転行動や停止(躊躇)を分析します。意思決定の迷いや記憶の確かさを評価する新たな指標となり得ます。
本記事のまとめ
Be-Chaseが提供する「停止」と「回転」の分析は、単純な活動量の変化だけでは見えてこない、行動の質的な側面を明らかにするための鋭いメスです。
- 「停止」分析は、フリーズや休息といった行動を定量化し、動物の不安、恐怖、記憶、覚醒レベルなどを評価する手がかりとなります。
- 「回転」分析は、サーキリング(回転運動)を定量化し、運動機能の異常や左右差、常同行動などを評価するための重要な指標です。
- 【複合解析】: これらの質的分析と空間分析(チェックエリア等)を組み合わせることで、行動の背景にある内的状態を、より深く、立体的にプロファイリングすることが可能になります。
これらの質的分析と、他の記事で紹介している空間分析(ヒートマップ、チェックエリア、ジニ係数など)を組み合わせることで、ターゲットの行動をより深く、多角的にプロファイリングし、研究の新たな扉を開くことが可能になります。
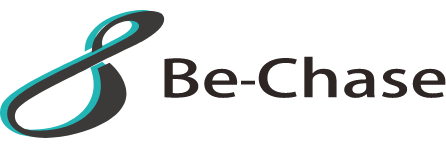
Be-Chaseは、いつでも誰でも簡単にプロ品質の行動定量化・分析ができる動画解析サービスです。実験データの客観評価を通して、研究者の『なぜ?』を次の発見へ導きます。
サービスの詳細はこちら>
